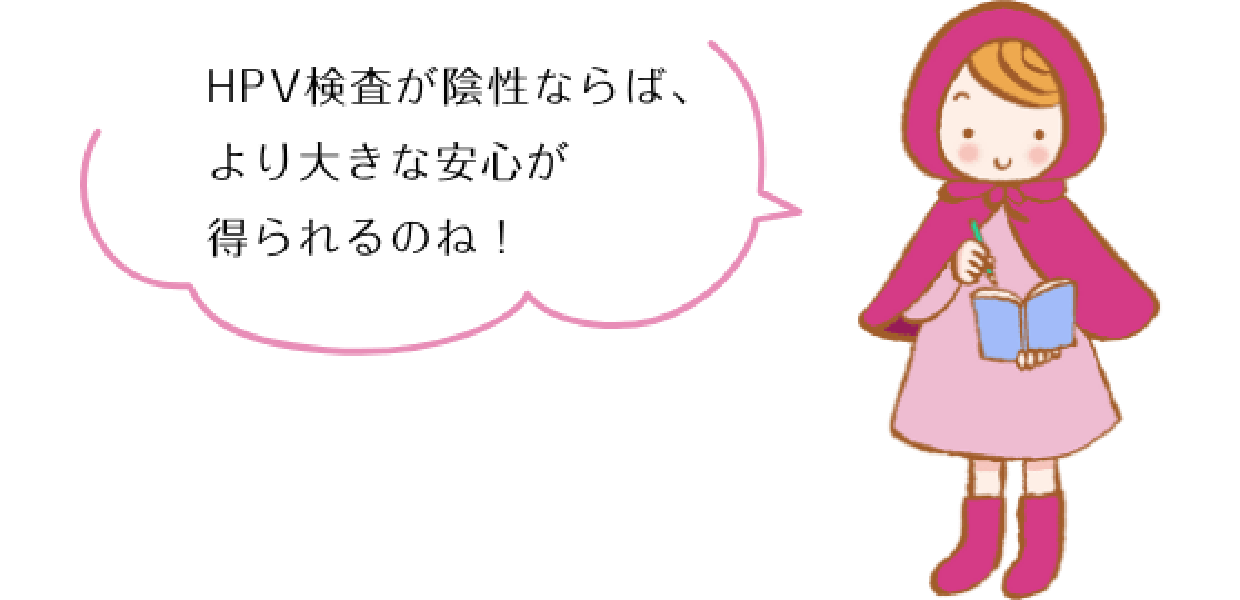子宮頸がんの検診
定期検診が予防につながる!よくわかる子宮頸がん検診

- TOP
- 子宮頸がんの検診
いつから検診が必要なの? 検診の内容は?
子宮頸がん検診について、気になる疑問にわかりやすくお答えします。
検診の基本情報
定期検診はいつから、なぜ必要なの?
20歳を過ぎたら、健康でも2年に1度の検診(細胞診)が予防の役割を果たします。
性交渉によるHPV(ヒトパピローマウイルス)感染から子宮頸がんに進行するまでには、およそ5年~数十年かかるといわれています。子宮頸がん検診はがんになる前の「異形成」の段階で病変を見つけることが可能なので、定期的に検診を受けていれば、がんに進行する前に発見することも可能で、予防と早期発見につながります。健康でも性交渉経験のある女性なら誰でも子宮頸がんになる可能性があり、初期の子宮頸がんには自覚症状がほぼありません。性体験が低年齢化している現在では、20歳を過ぎたら少なくとも2年に1度の検診(細胞診単独の場合)が大切です。
子宮頸がん検診の検査内容は?
子宮頸がん検査には「細胞診」と「HPV検査」があります。
子宮頸がんの原因はHPVの感染。でも感染しても、それががん化するまで長い時間がかかるので、その間に子宮頸がん検診による発見が可能なのです。そのためにも定期的な検診が重要で主に細胞診という方法で行われています。 最近ではこの細胞診に加え、HPVに感染しているかどうかを調べるHPV検査もあります。
検診が受けられる場所は?
婦人科クリニックや検診センターで受けられます
検診場所は婦人科クリニックや検診センターで受け付けており、健康保険組合や自治体が実施する検診の多くは、いくつか指定の医療機関から選んで受けられます。
検査にかかる時間は?
痛みはほとんどなく、30秒から1分で終わります
個人差はありますが、基本的には痛みもなく30秒から1分で終わります。細胞診、HPV検査のどちらも、子宮頸部の細胞を採取して検査します。採取方法はまったく同じで、綿棒やブラシで子宮入り口の表面を優しく撫でて細胞を採取します。息を長く吐くことを意識して、力を抜いてリラックスしましょう。
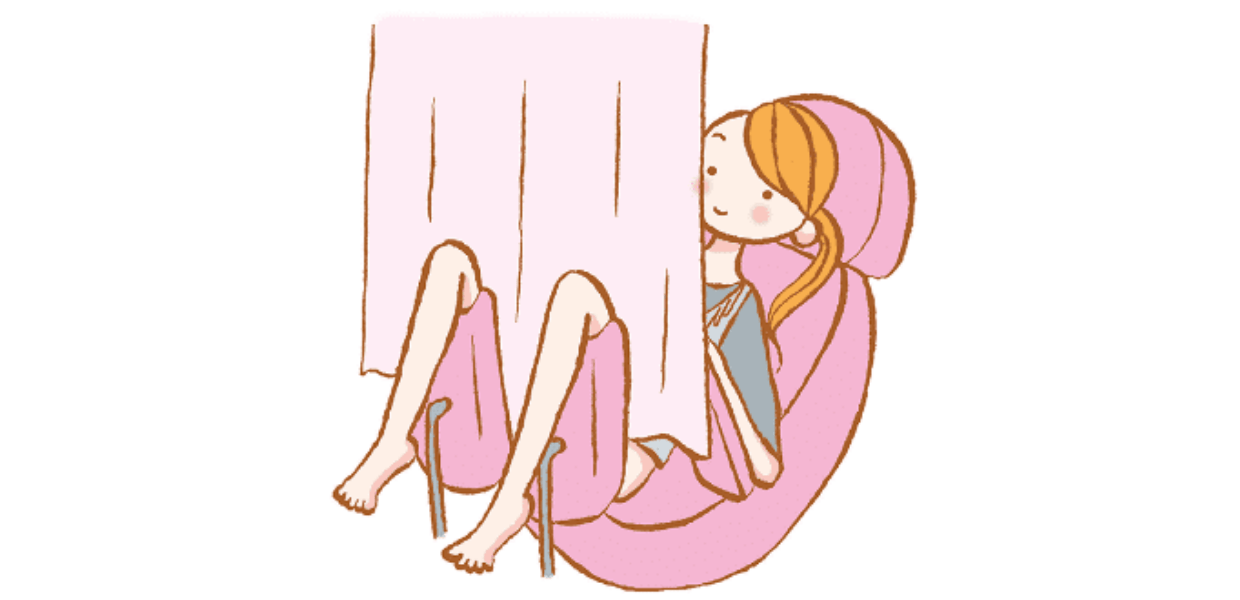
検査にかかる費用は?
3,000円~8,000円程度、助成金制度も利用できます。
子宮頸がん検診は「細胞診」のみの検査なら、自費の場合、3,000円~5,000円。「HPV検査」は別途、申し込みが必要で、費用は5,000円~8,000円くらいです。「細胞診」の検査で補助金を受ける場合でも、必要なお金を用意しておきましょう。
また、職場や自治体が全額または一部を助成してくれる場合があります。HPV検査はまだ試験的に行われている段階ですが、希望する場合は原則自費となります。まずはお住まいの市区町村、お勤め先の状況をチェックしてみてください。
細胞診
細胞診の内容
子宮頸部の細胞の変化を調べます。
一般的にいわれる「子宮がん検診」とは子宮頸がん検診のことで、「細胞診」という検査が行われます。子宮の入り口(頸部)の細胞を採取し、顕微鏡で調べる検査で、がん細胞だけでなく、がんに進行する可能性のある「異形成」といわれる細胞を発見することができます。そのため細胞診で検査結果に異常があった場合でも、がんになる前の病変の方がほとんどなので、異常があった場合はすぐに医療機関で精密検査を受け、詳しく調べてもらうことが大切です。
細胞診の判定結果(ベセスダシステム)
| 結果 | 略語 | 指定される 病理診断 |
従来の クラス分類 |
運用 |
|---|---|---|---|---|
| 陰性 | NILM | 非腫瘍性所見、炎症 | I、II | 異常なし:定期検査 |
| 意義不明な異型扁平上皮細胞 | ASC-US | 軽度扁平上皮内病変疑い | II-IIIa |
|
| HSILを除外できない異型扁平上皮細胞 | ASC-H | 高度扁平上皮内病変疑い | IIIa-b | 要精密検査:コルボ、生検 |
| 軽度扁平上皮内病変 | LSIL | HPV感染 軽度異形成 |
IIIa | |
| 高度扁平上皮内病変 | HSIL | 中等度異形成 高度異形成 上皮内癌 |
IIIa IIIb IV |
|
| 扁平上皮癌 | SCC | 扁平上皮癌 | V |
HPV検査
HPV検査の内容
ウイルス感染を調べます
細胞診と同じように採取した細胞を、検査キットを使って精密機器で調べる、最近始まった検査法。子宮頸がんの原因であるウイルス、HPVに感染しているかどうかがわかります。
このHPV検査を細胞診と組み合わせて実施することで、検診の精度はさらに高まるといわれていて、海外では併用検診やHPV検査で陽性の場合に細胞診をする国もあります。感染していれば「陽性」、感染していなければ「陰性」と診断されます。
HPV検査のメリット
HPV検査で確認できる、超ハイリスクのHPV16型と18型
子宮頸がんの主原因となるハイリスク型HPVは約15種類。そのうち、現在普及しているHPV検査で感染が確認できるのは、約13~14種類。特にHPV16型、18型が子宮頸がんに進展する可能性が高く感染した後の進行スピードも速いといわれています。(※) HPV検査では、超ハイリスク型ともいわれるHPV16型と18型への感染が確認できる方法もありますので、お医者様へ尋ねてみましょう。
- ※出典:Khan MJ et al. J Natl Cancer Inst. 2005; 97(14): 1072-9.
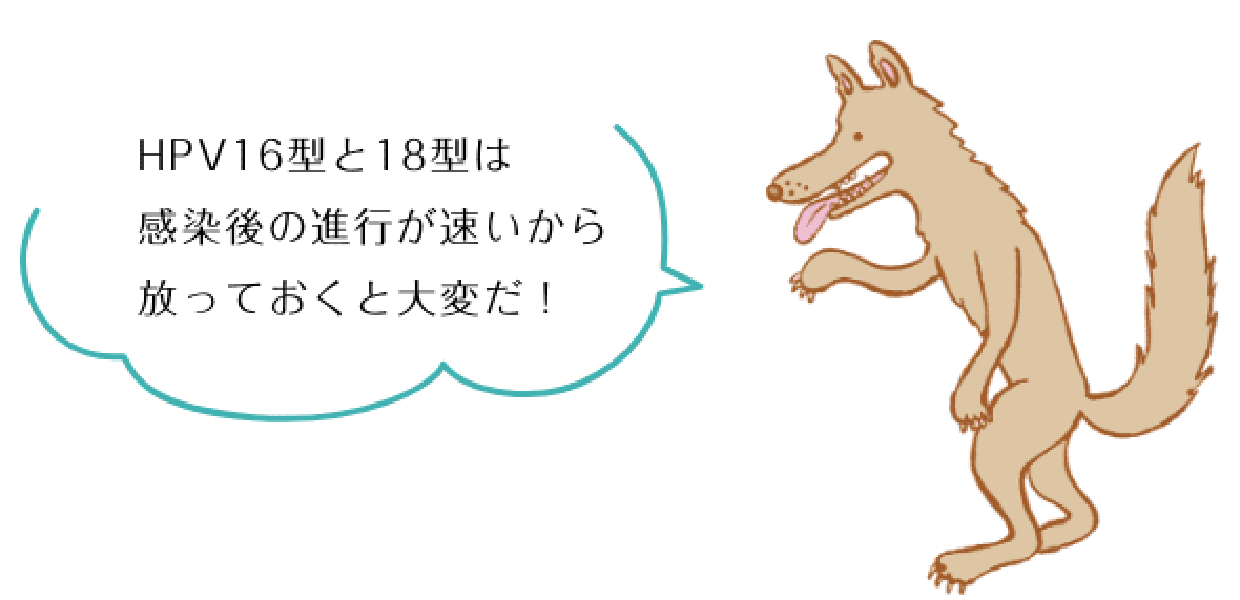
30歳を過ぎたら、HPV検査の受診も検討してみて
日本ではHPV検査は30歳以上の女性に推奨されています。検診方法は「HPV検査単独法」と、細胞診法とHPV検査を同時に行う「細胞診・HPV検査併用法」の2種類があります。HPV検査による検診は、細胞診と比べ「異形成」のリス クがある人を多く見つけられ、陰性の場合、次回の検診間隔を延長できるというメリットがあります。しかし、HPV検査による検診は、現時点で治療の必要がない人に対しても、将来のリスクも含め「陽性(感染)」と判定します。陰性の場合、より大きな安心が得られるHPV検査。現在日本では、20歳以上の女性に対し、厚生労働省が定めている「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」において、2年に1度の細胞診単独法を基本としていますが、一部の自治体や健診センターではHPV単独法に先行し、併用法が導入されています。興味があれば問い合わせてみましょう。